
| 記事:2019年3月 |
←1904
1901→
記事一覧(+検索)
ホーム

|
パトロクロスの戦争論〜シモーヌ・ヴェイユ『ギリシアの泉』(前)(2019.03.27)
古代ギリシャ・トロイア戦争の英雄たちを語りながら、彼女は現代の戦場を見ている。プラトンを語りながら、彼女はプラトンより昔の、失なわれた神秘の残響に耳を傾けている。
大阪・梅田は日本でも有数の乗降客を誇るだろうターミナル駅でありながら、同じ施設内に歩いていける古書店横丁「阪急古書のまち」を擁する稀有な場所だ。その名も梁山泊という一店で、今年の一月に入手したのが「シモーヌ・ヴェーユ」の『ギリシアの泉』(みすず書房)だった。
題名のとおり、ヴェイユが著した古代ギリシャ関連のテキストを集めたもので、冒頭の「『イリアス』あるいは力の詩篇」が、一行目から関心を引きつけた。いわく
「『イリアス』の真の英雄、真の主題、その中枢は、力である」
少し離れて、こう続く。
「力はそれに屈する者をだれであれ「もの」にしてしまう」
一見して、何かすごいことが書かれている気にさせられる。だが何のことやら見当もつかない。どうして、あのイーリアスから、そんなテーマを引き出せるのか。それは、読み進めると明らかになる。
『イーリアス』はトロイア戦争を歌った、ホメロスの叙事詩である(重い腰をあげて読んだのは昨年だか一昨年だかですが)。ブラッド・ピット主演で映画になった、そちらのほうを先に観ています。攻め手となるアカイアがたの面子に、英雄アキレスとその親友パトロクロス・強欲なアガメムノン・知恵者オデュッセウスなどなど。一方のトロイアは孤軍奮闘の勇者ヘクトールに、そもそも戦の原因となった軟派男パリス。ホメロスの詩じたいはヘクトールの死で終わり、アキレスのかかともトロイの木馬も、ましてアガメムノンの無残な死も、十年にわたるオデュッセウスのオデッセイも描かれないのだが…
この現存する最古の物語(のひとつ)を、もう少しクローズアップして現れるのは、引き際を知らない追撃者が逆襲を受けるシーソーゲームの繰り返しである、とヴェイユは指摘する。
獅子奮迅の活躍でトロイアがたを圧倒したパトロクロスは、そこで止まればいいものを、敵を深追いしてヘクトールの餌食となる。ヘクトールはそこで手打ちにすればいいものを、パトロクロスの遺体を辱めてアキレスの恨みを買う。そしてヘクトールを討ち取ったアキレスもまた、ヘクトールの遺体を辱め…
「このように暴力はこれに触れる者をおし潰す。
ついには、これを操る者にとってもこれを蒙る者にとっても外的なものとしてたち現れる」
『イリアス』の世界を厳密に貫く、この原理は神格化され、復讐の女神ネメシスと呼ばれる。なぜ誰も彼もが、敵が尻尾を巻いて逃げ帰る・終戦には絶好のチャンスを逃し、敵の全滅まで目論んで追撃しては返り討ちに遭うのか。それは、より戦利品が欲しいなどといった打算ではなく、より力を、力そのものを行使したい「過剰への誘惑」のためだと、ヴェイユは説いているかのようだ。
「出発のときは、かれらの心は軽やかである。(中略)
武器は自分の手の中にあるし、敵はその場に不在である。(中略)
いつでも人間というものは不在の敵よりはるかに強い」
こうした過信と、その過信で自ら泥沼にはまっての絶望は、(彼女にとって)現代の、西部戦線でも変わらない。さりげないヴェイユの指摘にギクリとする。
1909年に生まれ、43年に亡くなったヴェイユは、20世紀のヨーロッパで戦われた二つの世界大戦を両方とも、吾が事として体験している。古代ギリシャの探究は、彼女にとって現在から離れるための避難所ではなかった。ヘクトールやアキレスの運命を通しても、彼女の思索は結局、彼女じしんの現代と対峙していたのだろう。
ヴェイユは言う。たしかに人はみな死ぬが、死は未来を制限するものであって、未来そのものではない。だが戦場に駆り出された者にとっては死こそが、死だけが未来となる。
「これは(人間の)本性に反している」という、ヴェイユの言葉は力強く美しい。人は死を運命づけられてはいるが、生の本性は生きることにある。だが戦争は、その本性を人から剥ぎ取る。そして未来という、人間的な生の本性を剥奪された者の前で、敵の命乞いが何になるだろう?
「計算し工夫を凝らし決心をしてからその決心を実行に移す人間たちのあいだでは、戦闘というものは決着をみない。戦闘が決着するのは、こうした能力を剥奪され(中略)受動性にすぎない惰性的な物質(中略)にまで堕ちた人びとの間においてである」
これが力の本性である。別の著作で、戦争は、他国を攻撃し他国民を殺す以前に、殺し殺されることを自国民に強いる時点で悪なのだ、と説いたヴェイユである。力は人を「もの」に変える、という冒頭の言葉の意味が、ここに至って解き尽くされる。
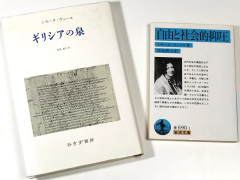
己の力に駆り立てられては裏切られ、最後は命乞いもむなしく刃にかかる男たち。まして、奴隷と同等の、つまりゼロの自己決定権しか持たない女たちの悲惨。これらの悲惨を、たとえば大いなる目的のための犠牲などとして正当化しない点で、際立つものとして『イリアス』はヴェイユの心を捉えた。
死を強いる「力」に屈従する人の悲惨と無力を、同等に哀惜こめて活写しえたのは福音書だけだとヴェイユは言う。神(キリスト)ですら、処刑を前に絶望する。死を恐れない殉教者たちは、神よりも偉大になったつもりなのかと。古代ギリシャとキリスト教、そして眼前の世界大戦が、彼女の眼中で収斂する。その先には、吾々じしんの「現代」がある。
亡命中のレーニンと論戦し、哲学者アランに師事した学生時代はボーヴォワールを蒼白たらしめたと言われる秀才シモーヌ・ヴェイユ。人を「もの」化する現代の欺瞞を冷徹にあばきながら、それを打ち砕く腕力は持ちえず、徒手空拳で産業社会に挑んでは消耗し疲弊し、追い打ちのように始まった二度目の世界大戦に打ちのめされ、衰弱死した。
彼女の著作にふれるたび「明晰すぎる悲劇」というイメージが頭をよぎる。
後編は、もう少し軽めの話になる予定です。
ソクラテスの師匠たち〜シモーヌ・ヴェイユ『ギリシアの泉』(後)(2019.03.28)
1980年代に生国フランスのガリマール社が全集の編纂に着手するまで、シモーヌ・ヴェイユの著作は専ら、アルベール・カミュが編集する選書から刊行されていたらしい。エスポワール(希望)選書というそうだ。色々と感慨深いものがある。『ギリシアの泉』をアルバムに例えると、シングルカットされるのは冒頭の『イリアス』論と、後半の山場となる「プラトンにおける神」の二篇だろう。
プラトンといえば、哲学の始祖である。というか無知の知を提唱し、産婆術で人々を啓発したソクラテスの言行を、プラトンが書き残した。それまで、万物の根源は水であるとか、数であるとか、原子であるとか唱えていた自然哲学者・あるいはソフィストと呼ばれる言い回しの専門家たちと一線を画し、ソクラテス(プラトン)は美とは何か・真とは何か・善とは何かといった人間の生きかたの学としての哲学を創始した。知を愛する(フィロソフィー)。汝自身を知れ。形而上学。イデア。…中学生や高校生が、学校その他で学ぶプラトン(ソクラテス)のイメージは、こんな感じだろうか。それまでの、迷信のようだった(ピタゴラスは教団の主だった)プレ哲学と隔絶した、理性の学としての哲学の確立。
ヴェイユの「プラトンにおける神」は、この常識をくつがえす。
「わたしの解釈では、プラトンは真正の神秘家であり、あまつさえ西洋神秘主義の父である」
ヴェイユはプラトンを、迷信を断ち切った哲学の創始者ではなく、師ソクラテスはもとより、オルフェウス教・エレウシスの秘儀・ピュタゴラス主義・さらにはエジプトやオリエント諸国に伝わっていた、今は失なわれた神秘思想の最後の継承者・記録者と捉える。「おそらく、ピュタゴラスやかれの弟子たちはさらにすばらしかったであろう」だが、それを証拠だてる、プラトン以外の文献が残存していないと言うのだ。
ヴェイユはプラトンのイデア論や、真理へのアプローチが、むしろ理性を超えた神秘主義への道であったことを例証してゆく。その詳細は本篇に譲るとして、たとえばプラトン「ファイドロス(パイドロス)」から彼女が引き出してくる一節は、たしかに理性的な哲学のための比喩というより、文字どおりに読めば神秘の様相を帯びる。
「ほんとうに実在する実在は、色もなく、かたちもなく、触れることができるようなものもない。
実在は、魂の主である精神によるのでなければ観照することができない」
「魂は身体をもつもののうちでは神的なものにもっとも近いのだ」
「完全で有翼の魂は空中をめぐり、全世界を統べる。
翼を喪失したものは、固い物体にぶつかるまで落ち続け、そのなかに棲みつく」
「翼の本質的な特性は、重いものを高みに運ぶことである」
これらのフレーズを引いたうえで「翼とは恩寵であることを、これ以上はっきりと言うことはできない」とヴェイユが評するとき、彼女の主著のひとつが『重力と恩寵』という題だったことが、今さらながらに思い出される。人は生まれる前の、神とともにいた記憶を失なってしまう…的な意味ではなく、もう単純に読んだ当時の無理解と忘却のせいなのですが(すみません)『重力と恩寵』とプラトンの関わりなど、とうに脳内から揮発しており、再読が必要だなあと思った次第です。はい、すみません。
代わりに思い出したのは、そういえば(プラトンの書いた)ソクラテスは、自らの師について、たびたび言及していた、ということだ。
「ソクラテス以上に賢い者はいない」デルフォイの神託で告げられたソクラテスが、そんなはずはない、自分などより賢い者がいるはずだとアテナイの街で問答を始めたところ、誰も彼の問いに答えられず、神託どおりの智者として名声と非難を集めていく…この「公式設定」はゼロからのスタート・既存の知識の蓄積や伝達とは違う「自分で考えること」を創始したソクラテス、というイメージを帯びている。
しかし、そんな先入観でプラトンの著作を読み始めると、時々引っかかることがあった。人々の目を醒まさせる彼の弁舌には「元ネタ」があったと、ソクラテス自らが語っているのだ。
「これは、ぼくが以前、マンティネイアの婦人ディオティマから聞いたところのものだ。
この女(ひと)は、恋のこと、そのほかのことなども多方面にわたる知者であって(中略)
ぼくに恋愛の道を教えてくれたのも、ほかならぬこの婦人である。
そこで、この女(ひと)が聞かせてくれた話を、諸君にも、できるだけ逐一お聞かせしてみたい」
(「饗宴」)
「ぼくが弁論術を習った女の先生は、けっして凡庸の人ではなく…
(メネクセノス「その女の先生とは、だれのことですか。いや、むろん、アスパシアのことをおっしゃっているのでしょうね?」)
そう、その人のことだ」
(「メネクセノス」)
プラトンは哲学の創始者ではなく、それ以前の神秘思想の継承者だった…そうヴェイユが断言するのを読んで、この、ソクラテスに教えた者たちのことが甦った。もっと言えば、ソクラテスに教えた女賢者たち。ウィキペディアによれば、ディオティマは哲学者であり巫女。(ソクラテスのみならず、ペリクレスの弁論の師でもあったという)アスパシアには、遊女という肩書きもある。
これはもう、ヴェイユの著作から切れた、自分の妄想の話なのですが、ソクラテスの師匠であった、巫女であり遊女・妓女でもある女哲学者「たち」が存在した、その起源はアテナイよりもさらに昔…みたいな小説や物語が書けないだろうか(自分が、ではなく「誰かが」だけど)という思いつきが、ヴェイユのプラトン論で少し息を吹き返し、さらに深みを帯びたのでした。
そして少しだけ妄想は古代ギリシャを離れ、20世紀のヨーロッパにつながる。ディオティマ、アスパシア、さらに沢山の名前が残存しない人びと。哲学者であり、巫女であり、遊女であり、プラトンより前、ソクラテスより前の、世界の秘密を知る女たちが、遠い遠い末裔・削り尽くした命を終えようとしている哲学の闘士を、その死の床に迎えに来る、蒼い蒼い海の彼方へと誘ないに来る、そんな1943年に…
自分が再読を期したい本。ヴェイユ『重力と恩寵』『ヴェーユの哲学講義』そして名著の誉れ高いコーンフォード『ソクラテス以前以後』。きれいに内容を忘れていることも、どれも自宅の本棚にあるはずなのに、探さないと出てこないのも情けない。
あと自分の「ソクラテスの師匠たち」構想に(読んでもない)のに影響を与えていそうな、中国の孔子一門がサイキック呪術集団だった(?)という小説にも、挑んでみようと思ってます。
| (c)舞村そうじ/RIMLAND |
←1904
1901→
記事一覧(+検索)
ホーム

|