
| 記事:2021年1月 |
←2102
2012→
記事一覧(+検索)
ホーム

|
読み比べ『神曲』3×3〜ルネ・ジラール『地下室の批評家』(2021.01.10)
1)翻訳×3自分には審美眼やセンスがない・日本語すら覚束ないと、前回の日記で言いはしたが、もちろん多少の判別はつくのです。同じ文章の翻訳なら
a.一切は機械をなしている。天空諸機械。天の星々や空の虹。アルプス諸機械。
これらの機械は、レンツの身体のさまざまの機械と連結している。ここにあるのは機械のたえまなく唸る音。
と
b.すべては機械をなしている。天上の機械、星々または虹、山岳の機械。
これらが、レンツの身体のもろもろの機械と連結する。諸機械のたえまないざわめき。
は、ちょっと違うな程度は分かる(ジル・ドゥルーズ=フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス』a…市倉 宏祐訳、b…宇野邦一訳)。
a.生い茂る栗の木の下で
俺はお前を売り、お前は俺を売った
奴らはあそこに横たわり、俺たちはここに横たわる
生い茂る栗の木の下で
と
b.おおきな栗の木の下でー
あーなーたーとーわーたーしー
なーかーよーくー裏切ったー
おおきな栗の木の下でー
だったら、なおさら分かるというものだ(ジョージ・オーウェル『一九八四年』a…新庄哲夫訳、b…高橋和久訳)。
とはいえ正直、どう違い、どちらが良いのか言語化するレベルには至っていない。初めて見た訳文を親だと思ってしまうこともあるだろう。平易で明快な訳を欲することもあれば、凝った美文に酔いたい気持ちもある。明晰さと詩的な美しさはバーターなのだろうか。

前回の予告どおり、かねてから懸案だったダンテ『神曲』三つの訳の読み比べに、いよいよ着手しようと訳本を揃え始めた。
そもそも『神曲』を読んでみようか、読書のレパートリーに『神曲』がある人生を送ってみようか、そう思ったのは須賀敦子氏の影響だろうか。四方田犬彦氏の影響だろうか。日本の文庫のように持ち運び容易なコンパクトな版でイタリア語の『神曲』を持ち歩く老婦人のエピソードを読んだのは、さてどちらの著書でだったか。地獄篇第五歌・愛ゆえに罪人とされたフランチェスカ・ダ・リミニの逸話が好きだという老婦人と、エッセイの語り手は飛行機で隣り合ったのではなかったか。
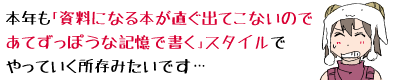
最初に読んだのは集英社文庫・ヘリテージシリーズの寿岳文章(1900-1990)訳だった。その特色は独特な語り口だ。
ひとの世の旅路のなかば、ふと気がつくと、私はますぐな道を見失い、暗い森に迷いこんでいた。
ああ、その森のすごさ、こごしさ、荒涼ぶりを、語ることはげに難い。思いかえすだけでも、その時の恐ろしさがもどってくる!
その経験の苦しさは、死にもおさおさ劣らぬが、そこで巡りあったよきことを語るために、私は述べよう。そこで見たほかのことどもをも。
後述するが、個人的には一番好きな訳だと思う。けれどただちに買い求めなかったのは「ますぐ」「こごしさ」と既に片鱗を見せている独特な語彙や、その語彙の中に(キリスト教文学の金字塔なのに)仏教用語を多用したと批判されていたため、ばかりではない。明晰さと詩的な美しさはバーターではないか。美しいがこの訳文だけで済ませて「寿岳文章の」でなくダンテの『神曲』を把握したと思うのは危険ではないか。
そんな思いで、実際に買い求め書棚に収めたのは河出文庫の平川祐弘(1931-)訳だった。
人生の道の半ばで正道を踏みはずした私が目をさました時は暗い森の中にいた。
その苛烈で荒涼とした峻厳な森がいかなるものであったか、口にするのも辛い。思い返しただけでもぞっとする。
その苦しさにもう死なんばかりであった。しかしそこでめぐりあった幸せを語るためには、そこで目撃した二、三のことをまず話そうと思う。
こうして見ると、寿岳訳だけだと若干ヤバいな、危ういなと思うでしょ?平易で読みやすい訳だと思います。
問題は、平易なぶん寿岳訳よりは感動が薄めなこと、そしてこれは全く訳文に影を落としてはいないのだけど、訳者の平川氏が自分とは相容れない=若干ヤバいな、危ういなと思う思想の主であること。簡単にいうと日本スゴイのひと。ダンテをここまで丁寧に訳し、その政治的背景まで解説できる人が、どうして私人としてはこうも固陋なのと失望させられた一方、国粋主義や表裏一体の他国蔑視に走るのは無教養なよるべない人々ばかりでない・知性も教養も人が固陋に陥らない保証にはならないのだ…という苦い教訓を与えてくれた訳者。最近では、菅首相による日本学術振興会への弾圧(というにもレベルの低いイチャモン・言いがかり)を支持しますという、櫻井よしこ氏が筆頭の宣言に名を連ねてしまってます。でもこの訳文は憎めない。逆に日本スゴイの人は訳よし訳者よしで万々歳…とは思いたくないけれど。
寿岳訳は1974-1976年。平川訳は1966年に初訳したものの改訂を重ね、全面的に見直したのが2008年の河出文庫版。
これら先達を凌駕する正しい訳と鳴り物入りで登場したのが2014年・講談社学術文庫の原基晶(1967-)訳。
我らの人生を半ばまで歩んだ時 目が覚めると暗い森の中をさまよっている自分に気づいた。まっすぐに続く道はどこにも見えなくなっていた。
ああ、その有様を伝えるのはあまりに難しい。深く鬱蒼として引き返すこともできぬ、思い起こすだけで恐怖が再び戻ってくるこの森は。
死にまるで変わらぬほど苦しいのだ、しかしその中で見つけた善を伝えるために、目の当たりにしたすべてを語ろう。
冒頭の一節はイザヤ書の「人生の半ばで私は地獄の門に赴いた」を踏まえたものだと訳注にある。「まっすぐに進む道」とはヨハネによる福音書の「私は道であり、真理であり、命である」の引用であると。そういう文脈があるので「まっすぐな道を見失った」だけで人生のことだと分かれよ―原文への忠実度が高い訳だとそうなるようだ。わざわざ「人生の道の半ばで正道を踏みはずした」と意訳してくれた平川氏の親切が改めて知れるし、訳としての精確さとニュアンスの伝わり加減も時にバーターなのかもと考えさせられたりする。
パッと見「エモさ」では平川訳にもまして感動の薄い生硬な訳にも見えるが(とゆうか寿岳訳がエモすぎるのだ)、まだキチンと読んでないので未知数。文芸的・詩的な喜びでは寿岳訳、平易さでは平川訳、考証の精確さでは原訳らしい…というのが暫定的な結論でよろしいか←いま流行りのブログ風に「いかがでしたか?」と書くのもアリかな、いやナシだろと思ったら、かわりに仕事の起案文みたいになってしまった…
ちなみに寿岳訳・平川訳では各章の前に簡単な要約がついてて親切です。
2)地獄・煉獄・天国
そんなわけで、読み物としては寿岳文章訳の『神曲』が抜群に「エモい」です。くだけた言い方を重ねてしまえば「キャラ立ち」が違う。人生の正道を踏みはずしたダンテが生きながらに地獄・煉獄・天国を踏破する。キリスト生誕以前に死んだので天国には行けないが地獄・煉獄に属することも出来ず「辺獄(リンボ)」に居る古代ローマの詩人ウェルギリウスがダンテの道行きを案内するのですが、このウェルギリウス(寿岳訳だとヴィルジリオ)が『千と千尋』のハク様なみに優しく頼れて萌える。天国には入れない彼が煉獄篇の最後で姿を消したあとのロスときたら。
一方、バトンタッチして天国の案内をするベアトリーチェ。ダンテ永遠の片想い相手・理想の女性として知られるべ樣ですが、終始優しかったヴィルジリオに比べ、そのドSなこと。「節穴だらけのおことの眼にも、はきと意味が見てとれるように」分かりやすく話しましょうとか、私を永遠の恋人と言いながら別の婦人に心を移しましたねと罵るさま、蔑みの冷たさが映えるのは寿岳訳ならでは。そもそも迷えるダンテが地獄煉獄天国を訪問できるよう取りなしたのは彼女らしいのですが、すでに魂が天界に属しているせいか、意外なくらい人間味が乏しい。
なので読んでいて楽しいのは煉獄篇。地獄篇はすごいぞ、スペクタクルだぞSFだぞという意見もあるのは知っている。個々人の好みでしょう。自分の場合は咎人に救いの余地のない地獄より、苦役は負うものの救われる希望がある煉獄のほうが読んでいて清々しく心に沁みる。そしてまだ人間の身に、天国篇はちょっと難解。地獄=スペクタクル、煉獄=癒やし、天国=お勉強、これが二つ目の×3。よろしいでしょうか。
3)フランチェスカ・ダ・リミニをめぐる解釈×3(2?)
ダンテの『神曲』。三人の訳者によって味わいが三様だし、地獄・煉獄・天国の趣もまた三様という話でした。
以下は余談で、読む人によって解釈がこうも変わるかという話。
先述のとおり地獄篇第五歌は愛欲で身を滅ぼした者が墜とされた第二圏を活写する。クレオパトラやトロイのヘレネー、トリスタンなど居並ぶこの地獄にありながら、なおも寄り添い続ける二人がダンテの注意を引きつける。フランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタ。フランチェスカはパオロの兄ジャンチオットの妻であったが、夫の不在中に情を通じ、戻ってきた夫に殺された。
寿岳の訳注によれば結婚は政略結婚でジャンチオットは醜男、断られないよう眉目秀麗なパオロを代理に立て求婚させたという。ボッカチオが記した同説をやはり是とする平川の注では、このエピソードがダヌンツィオや与謝野晶子などに愛されたと解説されている。
対して原の脚注は冷静だ。「パオロがジャンチョットとしてリミニに送り込まれ、フランチェスカが欺かれて結婚したという逸話は正しくない(中略)彼女が彼と恋に落ちるのは結婚後のことである」
原氏の立場はニュートラルと言えるが、「熾の火燃ゆフランチェスカのこの中にありとも見えて美しきかな」(与謝野晶子)のように賛美されたこのエピソードを「騙されてはいけない」と厳しく弾劾するのが、誰あろうルネ・ジラールだ。よくよく考えてみなさい、二人がいるのは終わりある償いの業に励む煉獄ではなく、救いの余地がない地獄ではないかと。
短めの文章を集めた『地下室の批評家』(白水社)の中でも、とくに短い一文「『神曲』から小説の社会学へ」は、『欲望の現象学』に連なる初期ジラールのエッセンスが10ページ足らずに凝縮されたエッセイだ。そのさらに前半部のみの『神曲』にふれたパートで、ジラールは言う。「今はわが身から取り去られた美しい容姿」とフランチェスカが語るように、二人はすでに肉体を失なった分身で、寄り添ってはいても真の結合は不可能であると。
さらに彼が指摘するのは、二人が不倫の恋に落ちたきっかけだ。「ある日、つれづれに、私たちはランチロットが恋のとりことなった物語を読みました(中略)読みもてゆくうちに、いくたびかふたりの眼は合い、顔は色変え(中略)こがれてやまぬほほえみが、思うひとの口づけを受けたくだりを読んだとき、永久に私と離れないあのひとは うちふるえ、私の口を吸いました」地獄でも引き離せない、真の愛で結ばれた二人?これが?とジラールは問う。ここにいるのはランスロットと王妃ギネヴィアの不倫の恋を本で読むうち、不倫の恋に落ち、物語の二人が接吻する場面で口づけを交わす男女だ。
『欲望の現象学』で描かれた、騎士物語を模倣して愚行を繰り返すドン・キホーテや、恋愛小説に憧れて破滅するボヴァリー夫人と同様、『神曲』の二人も物語に影響されコピーした欲望で身を滅ぼした男女でしかないとジラールは裁定する。フランチェスカはこう語る。「その物語の書(ふみ)と、物語の作者は、げにガレオット」ガレオットはランスロットをそそのかし、主君アーサーの王妃ギネヴィアとの不倫の恋を取り持った不忠の騎士だとジラールは解説する。これは自分たちをそそのかした書物を糾弾する、フランチェスカの呪詛として読まなければいけない。
己の欲望は、本当に自発的なものか。初期ジラールが説いたのはそれを疑うことだった。すでに皆様お気づきのとおり、自分が『神曲』を手にしたきっかけは、このイタリアの古典をこよなく愛する人たちのエピソードを「読んで」その「欲望を模倣」したからに他ならない。三種類の訳をすべて手中にし、比較しようという今回の日記のネタも、前回の日記で記したとおり、『センセイの鞄』三書体の読み比べという楽しげな遊びを見て「真似したくなったから」。
面映い話である。
追記)
オーウェル『一九八四年』の「憎しみの歌」については、以下のブログに詳しい。自分のテキトウな日記などより、よほどキチンとした文章です。
・テレスクリーンと黄色い調べ『一九八四年』既訳のまちがいについて(野菜生活)(外部サイトが開きます)
高橋訳では「大きな栗の木のしたで」が元ネタとして、新庄訳ではそうした元ネタなしで直訳された「憎しみの歌」が、実は別の元ネタをもっていたという説得力のある話。自分は原詩There lie they, and here lie weのlieが新庄訳では「横たわる」になってて、それはそれで詩的で美しいのだけど、この場合「嘘をつく」のほうのlieなんじゃないかなーと思っていた節があって。高橋訳は「嘘」を採用してると思われる一方、件のブログに紹介されてる元ネタにはThere we sit both you and me座る、という単語がほの見えることから「横たわる」にもまた1ポイント入ったか、難しいなあと思っているところ。
ちなみに新庄訳の「横たわる」って本当なの?と思ったキッカケは、デヴィッド・ボウイの「ヒーローズ」終盤の一節がWe may be lying, then you'd better not stayのlieが「嘘をつく」だったから。愛を貫こう、一日だけでも英雄になれる、そう言ってる自分たちの言葉だって「嘘 lying」かも知れない、だったら君はもう僕と一緒にいないほうがいい…
ちょっとルネ・ジラールの「己の欲望は、本当に自発的なものか」と響き合ってるな、と感じてもらえたなら幸いです。本当はボウイの話まですると追記が長くなりすぎるとも思ったけれど、本日1/10は『一九八四年』とも縁のある彼氏が天に戻った日なので、まあ偲ぶキッカケになればと。
来週は、後期ジラールとアメリカ大統領選挙の話をする予定です。
満場一致が示すこと〜ルネ・ジラールで読むアメリカ大統領選挙(2021.01.17)
われわれは、ケーアス、生贄を捧げるものでありたい、屠殺者ではなく。(『ジュリアス・シーザー』第二場第二幕・小田島雄志訳)
供犠の時を四年間、待ち焦がれていた。人々の心が憎悪で沸き返り、偽物の王を処刑台に追い上げる日を。そのような日を待ち望んではならないと、強く戒められていたにも関わらずだ。
* * *
その論評を、個々人の欲望・羨望にまつわる考察から始めたルネ・ジラールは、しだいに思索の対象を社会的・文化人類学的な分野にまで広げていった。『暴力と聖なるもの』『世の初めから隠されていること』『身代わりの山羊』…中期の著作群でジラールが大きな関心を示すのは供犠=スケープゴートの問題だ。
ジラールによれば・羨望=互いの模倣による競争がエスカレートし極限に達するか・疫病などの社会不安で共同体は危機に瀕する。
「同一性、画一性のなかにいつでも一切を落ちこませるものは、逆説的ながら、他と異なろうとする欲望です」
(『世の初めから隠されていること』)
親子や兄弟姉妹さえ互いに競争しあう、ただの「敵」になる。誰をも等しく襲う疫病が、個性や肩書きを無力化する。そのようにして共同体は無秩序な、いわば「モブ」の集団になる。沸騰寸前まで熱せられた分子のように、水の一滴も投げ込んでやれば暴力の応酬=社会の崩壊につながる危機だ。
この危機を解消する魔法が、スケープゴートの追放だとジラールは言う。社会不安・互いの憎悪の理由を誰か一者に押しつけ、満場一致で追い出すことで、無秩序だった顔のない群衆が共同体としての秩序を一気に回復する。
重要なのは、この放逐が「満場一致」でなければならないことだ。そうでなく中途半端な、総員の同意を得られない「あいつを追い出せ」は、すぐに「お前こそ出ていけ」と模倣され、暴力の応酬に拍車をかけるだけだろう。
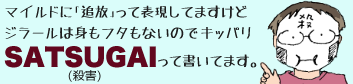
初期のソネットから晩年のロマンス劇まで、シェイクスピアの諸作をジラール流に解釈した『羨望の炎 シェイクスピアと欲望の劇場』(小林昌夫/田口孝夫訳・法政大学出版局)によれば、戯曲『ジュリアス・シーザー』は、まさにスケープゴート劇=供犠のメカニズムを体現しているという。
平日に仕事着も着ず、職務を放り出してシーザーの凱旋を見物に行く大工たちを描いた冒頭は(ジラールに言わせれば)秩序が崩壊し人々がモブと化した社会の危機を描いている。細かいことを端折ると、憂国の士ブルータスは共和制ローマを崩壊から救うため、シーザーをスケープゴートに仕立て、彼を粛清することで秩序の回復をはかろうとする。
だが続くのは暗殺が「満場一致」の賛同を得られなかったため、人々が陥るさらなる混乱だ。シーザー暗殺の義を説くブルータスの演説が、シーザーの腹心であったアントニーの弁舌によって覆され、聖なる生贄を捧げる供犠だったはずの暗殺は、ただの屠殺として人々の激昂を呼ぶ(ブルータスの仲間と同じ名前だっただけで、無関係の詩人が虐殺される)。この混迷に蹴りをつけるのは、皮肉なことにブルータス自身となる。アントニーと、シーザーの養子オクテーヴィアスの連合軍に破れ、自害した彼を勝者たちは
「彼こそ一味のなかでもっとも高潔なローマ人だった」(アントニー)
「その徳にふさわしい遇しかたをしよう、できるかぎり礼をつくして葬儀をおこなうのだ」(オクテーヴィアス)
と聖別する。言うまでもなく英語表記のオクテーヴィアスが、後にアントニー=マルクス・アントニウスをアクティウムの海戦で破り、初代ローマ皇帝アウグストゥスとなるその人だ。
まとめて言う。シェイクスピアの戯曲は・共和制ローマ崩壊の危機を・シーザーをスケープゴートにすることで救おうとしたブルータスが(満場一致の同意を得られず)供犠に失敗し・さらなる暴力を呼んだあげく・ブルータス自身が理想のスケープゴートとされ・彼が望んだ共和制の再生でなく逆に危惧した帝政の誕生により秩序が回復される…そんな皮肉に満ちたドラマとして読み解くことができる。
問題は、この供犠=スケープゴートの追放や処刑による秩序の回復を、ジラールが賛美も推奨もしていないことだ。
おおよその理解では、ジラールは次の二点で供犠の無効化を説く。ひとつは法の支配が広まることで(供犠を必要とするような)際限のない報復の連鎖に歯止めがかかること。
もうひとつは、相互模倣が対立や暴力に帰結せず、むしろ競争の激化が経済を駆動する稀有なシステム=資本主義が世界に定着したことだ。もっとも資本主義は、引き換えにその成員たち(互いのマウンティングに終始し、誇示的消費をやめられない吾々のことだ)に絶え間ない神経症をもたらす。だが古い供犠のシステムを復活させて、この新しいメカニズムを停めることは不可能だし、望んではいけないことだとジラールは説く。彼は言う。
「人間は供犠を介することなしに永遠に和解しあわなければならない(中略)
さもなくば、人類の近い将来における絶滅を甘受しなければならないのです」
…『世の初めから隠されていること』(原著1978)年の発言には、競争社会が生んだ環境破壊や、当時は東西対立のため今よりずっと切迫していた核戦争への懸念が反映されているだろう。しかしなお「和解」はスケープゴートを伴うもので、あってはならない。
なぜか。もちろん排除されるのがシーザーひとりでも暴力は暴力なのだが、現実の「供犠」はずっと多くの、それも王ではなく貧者や弱者・女性や子ども(ジラール言うところの「すべての犠牲にされやすいもの」)の、そして放逐では済まず殺害によって成る。戯曲の中のアントニーとオクテーヴィアスすらブルータスを討伐する前に、手付金のようにローマの元老院議員100人を粛清した。中世のペストに怯えた人々のユダヤ人排除、フランス革命にともなう恐怖政治、関東大震災後の朝鮮人虐殺、ナチスによる人道的犯罪…
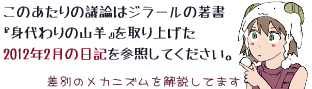
* * *
かようにジラール自身によって戒められているにも関わらず、自分は四年間、スケープゴート放逐の儀式を待ち望んでいた。2020年、アメリカ大統領選挙によってドナルド・トランプが追放される日を。
かの人物が選挙で勝利した2016年は、絶望の年だった。もちろん、煮えくり返っていたのは2012年からだ。太平洋の向こうではない自分の足元のことで八年間、絶望しっぱなしだった。国会前に60万人の群衆が押しよせ岸内閣を退陣に追い込んだような、隣国の韓国で百万人のデモが朴槿恵政権を倒したような「満場一致による追放」は、今の日本には期待できない。それが制度によって合法的に可能である・人々がまともならば四年後には陶片追放のチャンスがやってくるアメリカが羨ましかった。
いや、わりと冗談ではないのだ。今回の選挙で、開票にまつわる云々に人々が一喜一憂していた頃、ずっと考えていた。アメリカの大統領選挙とは、流血をともなわない形で洗練された、合法的な供犠=スケープゴートの放逐による共同体の秩序回復の儀式ではないかと。
もちろん眉に唾をつけていい。大いにつけなさい。望ましいのは他人の言ったことの鵜呑みや・まして呑み込みもしないコピペの同調ではなく、誰もが自身で考えること。だから自分も考える。ヒントになるのはアメリカの大統領選挙を(日本から見て)分かりにくくしていると言われた、州ごとの選挙人総取り制度だ。
たとえばペンシルバニア州に50人の選挙人がいるとして、州の選挙で共和なり民主なりの候補が競り勝つと、たとえそれが一票差の半々でも「じゃあ26対24にしましょう」ではなく勝ったほうが50人総取りになる。それは「アメリカ」と吾々が呼ぶ国家がUnited States(州の集合体)であり、州の自主性・自律性が重んじられていることを考えると、不思議と腑に落ちることでもあった。それぞれの州がひとつのState(国)であり、その決定は満場一致でなければならない。スケープゴートの追放の他に、こうした満場一致が求められた場を、吾々は知っている。現代の民主主義が(今では現実的でない)理想と仰ぐ、古代の民会だ。
大統領選における州ごとの選挙人総取り制度・の根幹にあるのは、古代の民主主義の理想である満場一致を、後からこじつける形でも、擬似的でも再び顕現させようという儀礼的な意図ではないか…というのが自分の仮説だが如何か。
そして改めて、この満場一致はスケープゴート追放(による秩序回復)の満場一致と同じものだ。血なまぐさい生贄の儀式と違う(けれど本質的には同じな)のは、昨日まで選挙を争っていた対立候補が、自ら最も重要な「満場一致」の先導者となることだろう。通例、選挙の結果が決すると敗者は真っ先に「勝者と一丸となって今後四年間のアメリカを作ろう」と自らの支持者に訴える。勝者もまた敗者の支持者たちに「あなたたちと一緒に今後四年間のアメリカを作ります」と呼びかける。かの国の大統領選挙を、国が真っ二つに割れる「合法化された内戦」とも称するらしい。自分が付け加えたいのは「流血をともなわない、洗練された供犠の儀式」でもある、ということだ。
もちろん再任もあれば、同じ政党で大統領職が継承されることもある。だが原理的には四年ごとに、前任者の完全降伏と放逐によってアメリカは、歴代の大統領が(つまりアメリカ自身が)為したあらゆる悪政も失政も「チャラ」に出来る。道を誤り、失敗した大統領はいるが、彼(将来的には「または彼女」)は満場一致の儀式によって正しく追放され、アメリカという理想・アメリカという理念は傷つかない。これはたいへんな巧緻にして狡知ではないか。
だいたい、そんなことを考えていた。だからトランプや支持者たちが実際には吾々が勝った・不正によって負けたと称しても、いちいち呼応して一喜一憂しようとは思わなかった。アメリカはバイデンを、と言うよりトランプ追放を選んだ。これは満場一致の選択だったと、歴史は後づけで認識するだろう。どれだけトランプやQアノン(敵対者の陰謀を信じるトランプ支持者)やJアノン(なぜか日本でトランプを応援する人たち)が悪あがきしようと、アメリカという制度は最終的には秩序を取り戻す。あるいは、それに失敗すればアメリカは崩壊する。それだけのことだと言えるし、自分には「アメリカ滅びろ」と思う積極的な理由はないので、秩序の回復が「まずは」望ましいと考える。
ではなぜ「まずは」と留保をつけるか。四年ごとに供犠を行ない秩序を取り戻すアメリカという国の、供犠を必要とする無秩序ではなく秩序もまた、信用できないと思うからだ。
ジラール自身は語らなかったが(そんなこと言ったら大統領選のことだって語ってない)「供犠を介した和解」ではいけないと彼が強く否定したのは「そうした和解が結局は破局を回避しえない」事例もまた多かったからではないか…そんな風に邪推したくなる。アウグストゥスが治めたローマは知らない。だがマリー・アントワネットからロベスピエールまで数多の首をギロチンで落とし、血まみれでようやく勝ち取ったナポレオンの下の秩序はフランスに、国民一丸となっての対外戦争・行かなくてもいいロシア遠征まで含めた殺戮と消耗を強いた。スケープゴートとしてユダヤ人を絶滅収容所に送ったナチス・ドイツ、朝鮮人を虐殺した日本が「満場一致」で邁進した自滅への道については言うまでもない。
アメリカが大統領選によって「満場一致」で・だが平和裡にスケープゴートを追放し秩序を取り戻す、それは大いにけっこうだ。だが秩序を取り戻したアメリカはベトナムで中東で、「満場一致」のアメリカは世界中で何をしてきたか。常に己の過ちを修正し、マイノリティに門戸を開き、より民主的・より多様な人々から成る社会として自らをアップデートしつづけるアメリカは同時に、常に外部に討伐すべき「ならず者国家」を設定し、満場一致の愛国心で焼夷弾を、ミサイルをドローン爆弾を、生命ある人々の上に落とし続ける、世界で最も好戦的な国家でもある。
その好戦性は、制度化された=社会の運営の根幹にまでビルトインされた供犠の儀礼の(洗練され押し隠された)残虐性・ジラールが批判しつづけた「満場一致」の暴力性と本当に無縁なのだろうか。
アメリカが今回の試練も乗り越え、トランプの放逐に成功し、秩序を取り戻すことを(四年間その存在に煮えくり返っていた身として)心から願っている。だが個人的には、アメリカという国家自体に、まだ気を許すことはできない。
Jアノンが奇論・こじつけを弄して他国の大統領(それも敗けた)を信奉するのが滑稽なように、世界に暴力をアウトソーシングしている「アメリカの正義」を、民主主義を求める非アメリカ人は過大評価=無条件で賛美し、己の手柄のように誤認してはいけないと思う。それが自分の頭で考える者の矜持であり、自力で(国内の)民主主義と秩序回復を勝ち取るだろうアメリカの人々への敬意でもあると。
(24.11追記:勝ち取れませんでしたねえ…)
明るいディストピア〜フランソワ・トリュフォーと星新一(2021.01.24)
「リルケがアポロンの像を眺めたとき、アポロンは詩人に語りかけました。「お前は生き方を変えねばならない」」(アーシュラ・K・ル・グウィン『夜の言葉』)
* * *
ディストピアという言葉で、思い浮かぶのはどんな光景だろうか。灰色に暗くよどんだ空。巨大スクリーンに映し出される独裁者。絶望に打ちひしがれた人々の顔、顔…
書物が禁じられた世界、という設定で「ディストピアっぽいイメージ」の典型のひとつとして愛されているのがレイ・ブラッドベリの小説『華氏451度』だ。もちろん、そこには言論統制や焚書・文化破壊への憤りや、異議申し立てがあるのだろう。だがフランソワ・トリュフォーが1966年に映画化した作品は、吾々が(実は心地よい悲劇として)愛好している「ディストピアのイメージ」を「えっ」と脱臼させるものだ。言いかえると、らしくない。失敗作だという声もある。だが逆に「本当のディストピアとは、こういうものではないか」と思って観ると、意外な発見がある。

映画のスタッフや出演者が長いエンドロールではなく、冒頭のタイトル・シークエンスで表示されていた時代。電波の送受信をイメージさせるアンテナが次々と映し出され、文字のかわりにアナウンスがクレジットを読み上げる。映画は全編にわたり、数字以外の文字が追放された社会を描く。ついでに言うと、この社会では若い男性の長髪も禁じられている(笑)。自由が抑圧された管理社会。だが冒頭、禁じられた書物を隠していたモブキャラが「逃げて」という電話の密告を受け、泡を食って逃げ出すシーンから違和感がある。自宅で煙草を喫い、リンゴを頬張っていた男は慌てて上着を着込むが、青々としたリンゴの続きをかじりながら逃走の途に就くのだ。
なんだろう、この場違いに牧歌的な感じは。そんな違和感が積み重なり、頂点に達したのは主人公の家のバスタブの蛇口を観たときだった。

黄金色のお魚がゴパーとお湯を吐き出す蛇口。こんな「ディストピア」があるか!その瞬間、違和感が弾けて理解に変わる。これは自分が思いこんでいた「抑圧された人々の陰鬱なディストピア」じゃない。少なくとも、チョコレートの配給量が日々減らされ、しかし情報操作で逆に増えてるように改変されている『一九八四年』モデルの窮乏ディストピアとは違う。人々は豊かで、満悦して、まあ主人公の妻は向精神薬を過剰摂取している傾向はあるが、それも含めて現実の吾々と変わらない、なんなら幸福感にあふれた社会・「明るいディストピア」なのだ。
【窮乏なき、明るいディストピアでも、あなたは本を読むか】(仮)
たかだか蛇口ひとつで映画の内容を決めるのはどうよ、と思うひとがいるかも知れない。では次のエピソードはどうだろう。主人公の妻が「無害な薬」と同様に手放せないのはテレビだ。番組の中に「家族」という視聴者参加型の特別プログラムがあって、彼女はそれへの「出演」を心待ちにしている。内容は双方向型を模した、しかし悲しいほど陳腐なものだ。二人の出演者が人々をパーティーに招く相談をしていて、時々「こちら」を向いては画面に問いかける。「リンダ、君はどう思う?」。
国内に20万人はいる「リンダ」全員にTV局が電話をかけ、あなたが出演者ですよと告げてるのだろうという主人公の邪推はおそらく正しい。それに気づかないリンダ(妻)が、どうとでも答えられる質問にしどろもどろに答えると、画面の向こう側の俳優は口々に「そうだ」「まったく彼女の言うとおり」と同意し、最後に呼びかける。
「リンダ、君は本当に素晴らしい」

なにしろ昔の映画なので「双方向のコミュニケーション」はかくも稚拙で、わざとらしい。だが寓意は正鵠を射ている。たあいもないトリックに喜ぶリンダを嗤う吾々も、切望し、そして手に入れてしまったのは同じメッセージではないか。半世紀後の吾々がキュレーションと称してインターネットで築き上げたのは、自分に心地よい情報ばかりが増幅されるエコーチェンバー、まさに「君は素晴らしい」というメッセージに(ばかり)あふれた世界ではないか。
窮乏なき、明るいディストピアでも、あなたは本を読むか(仮)→(改訂版)【自分自身が明るいディストピアの住人であることに、あなたは自覚的か】
* * *
前回の日記のために『ジュリアス・シーザー』を読み返して、懐かしいフレーズに再会した。シーザーを暗殺の現場に誘い出そうと謀議をめぐらす一味のひとりが言うのだ。
「象なら落とし穴、ライオンなら罠、人間なら追従を使えばいい(中略)
あなたは追従がきらいですねと言ってやれば、そうだと答える、それがいちばんの追従だと気づかずにな」(小田島雄志訳)
シェイクスピアの戯曲は未読でも、おおよそ日本語圏で本が好きと自称するなら、別の形でこの言い草を知ってる人は少なくないはずだ。つまり
「ほとんどの人が
「あなたのようにおせじのきらいなかたは、めったにございません。なんという高い見識でしょう」という文句で陥落した。
これはシェークスピアの「ジュリアス・シーザー」の中にもある文句だそうだが、
ことほめ言葉に関してだけなら、妖精も文豪に匹敵する天才といえた」
星新一のショートショート「妖精配給会社」の一節だ。同名の作品集(新潮文庫)の表題作で、個人的には星新一の最高傑作だと思っている。
説明の必要があるだろうか。妖精とは、宇宙から飛来した生命とも何ともつかない・しかし実体のある存在で、人の肩にちょこんと乗る大きさのそれらは実際に人の肩に乗り、持ち主の耳に甘いほめ言葉をささやく。それを一人ひとつ持てるよう公社のような会社が設立され、やがて誰もが肩に妖精を乗せるようになり、そして…という物語だ。
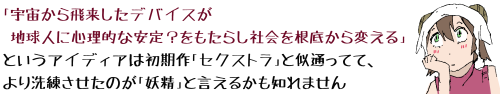
戦慄の結末については、ここでは述べない。真鍋博による新潮文庫の表紙に描かれた、うつむく「妖精」の容姿が天使や妖精より、むしろ地球の反対側で書かれた(やはり)SFの名作『幼年期の終わり』の「あれ」を思わせることも。いま述べておきたいのは、妖精を肩に乗せるかわりに吾々はスマートフォンを手に持ち、いわば自分とネットの共同作業で作り上げた「自分仕様の妖精」に日々「あなたは素晴らしい」と追従を囁かせている、ということだ。同作が星新一の(個人的に選ぶ)最高傑作という思いはずっと昔からのものだが、ネット時代・SNS時代になって、その辛辣さはますます際立っている。
* * *
トリュフォー版『華氏451』は寒々とした森に隠れ、これと選んだ書物の暗誦につとめる・自ら一冊の本となることを己に課した人々の姿を描いて終わる。このラストシーンを美しくしている要素は二点。トリュフォー自らの述懐によれば想定外に降ってきた雪と、主人公が選んだ書物の一節をめぐるエピソードだ。
台詞すべて英語で収録された同作の最後で主人公が暗誦するのはアメリカの作家エドガー・アラン・ポーの一節。だが撮影する段になって、ポーの原典には該当するフレーズがないことが判明する。実はフランス人のトリュフォーが使おうと思った「ポーの一節」は、同作をフランス語に訳したボードレールの勝手な加筆だったのだ。そこでトリュフォーはどうしたか。ボードレールが創作したフランス語の「ポー」を逆に英訳しなおして、主人公に朗読させてしまう。
公式な世界ではなく、個人の親密な記憶に重きを置いた、トリュフォーらしいエピソードだ。翻訳もひとつの創作という意味での佳話でもある。だが吾々はあらためて、そうまでしてトリュフォーが主人公に読ませたかった一節に注意を払わねばならない。それはこうだ。
「I'm going to relate a tale full of horror (私がこれから語るのは、恐怖に満ちた物語だ)」
お前は生き方を変えねばならないと、アポロンの像は詩人に告げた。ある意味で、それは多くの詩・多くの物語や書物・世界を行き交う言葉が発しているメッセージだ。生き方を改めろ。今までの自分でいるな。今まで知らなかった世界の住人となれ。
テレスクリーンや肩に乗った妖精がささやきかけるのは、それと真逆のメッセージだ。あなたは今のままでいい。手持ちの世界を反芻しなさい。何も変えず、何も新たに知ろうとせず、閉じた自己満悦に浸っていても、今のままであなたは素晴らしい。この国に限った現象ではないのかも知れない。だが、本来は「ありのまま」で「なかった」自分を変えようと謳うエルサの決意すら、「あなたは今までどおりでいい」という意味に曲解されるのを見て、とりわけこの社会では皆、自分を許したがりすぎると思ったのも確かだ。
トリュフォーのラストが告げるメッセージは、本好きな(気分でいる)だけであなたは不屈のレジスタンス・世界のヒーローなのですという欺瞞を打ち砕くものとして捉え直されるべきだろう。書物を愛するものは黄金の蛇口がお湯を吐き出す心地いいバスルームから追放され、凍えた森に身をしりぞける覚悟を持たねばならない。そこで開かれる物語は未知の、それまでの自分を壊してしまうような、恐怖に満ちた物語でなければならない。
本を愛するとは、そういうことだ。悪く言えば、次こそは足が生えてくるかも知れないと脱皮を繰り返す蛇のように。読むことで違う自分になる・違う世界の住人になることを望んで未知の扉を開く、そのような読書こそが読書なのだと、アポロンはあなたに告げる。
もちろん、そうでない慰撫を書物に、物語に求めることもあるだろう。僕だってある。しかし「あなたは素晴らしい」とメディアに甘やかされる愉悦と、「本を読む自分は管理社会に抗するレジスタンスだ」という慢心は両立しえない。いや、本来なら両立しえないからこそ、人は両者を両立させ、甘やかされながらレジスタンスを気取る欺瞞に落ちこみうるのではないか。だとすれば、それこそが吾々の心の中から始まるディストピア・心地いい管理社会ではないのか。
たえず甘言をささやく妖精が宇宙から飛来するのを待ちきれず、結局は自力で作り出してしまったのが吾々だ。ディストピアは、ひとり一人の心の中にある。
久しぶりに観直したトリュフォー版『華氏451』、「明るい」ディストピア映画なのだと承知して臨めば個々の描写も面白く、最後まで退屈しない良作でした。読書にのめりこみ、どんどん家庭を破壊してゆく主人公を観ると「本は人を不幸にする」という焚書官の隊長の台詞のほうが本当にも思えてくる、複雑な味わいを楽しみましょう。
息もできない〜グレゴリー・フィーリィ『酸素男爵』(2021.01.31)
まだ可能性の段階だと思いたいが、おそろしいニュースを読んだ。植物の光合成=二酸化炭素(CO2)を吸収し酸素を排出するはたらきは、ふつう温度が上昇すると活発化する。だが、ある温度で酸素排出量の「増加」は止まり、それより高温になると「低下」に転ずるというのだ。一方、植物にも当然ある生物としての呼吸=CO2排出の気温上昇による「増加」には限界がない。このまま地球温暖化が続けば、呼吸によるCO2放出が光合成による吸収を上回り、熱帯雨林や北方林など地上の植物群は(動物としてのヒトや、人の産業活動と同様)CO2を吐き出す側になる…アメリカの科学誌に発表された研究である。
・温暖化で2050年には森林がCO2放出源に、研究(AFPBB NEWS/2021.1.15)(外部サイトが開きます)
繰り返し言うが、あくまで研究の段階(と、思いたい)。自分個人に限って言えば、そうでなくても2050年まで生きてる気がしない。だが「吾なき後なら洪水が来たってかまわない」というエゴを捨てねば、温暖化の果てに森林火災や海面上昇ばかりでない「全人類窒息」が待っている(かも)というのは、あまりに哀しく、おそろしい未来図ではないか。
* * *
そこまで考えて、地球の未来ではなく(そういえば『酸素男爵』というSFがあった…窒息する前に読んでおきたい)と思いが横すべりするのが本サイト運営者の残念なところです。
今はなき吉野朔実さんが『本の雑誌』に連載していた読書エッセイまんがで取り上げていた本。いや「酸素男爵!?なにそれ!」と書名に惹かれた吉野氏だったが在庫切れで手に入らず、あれこれ自分で想像したあげく「読みたーい!読んでがっかりしたーい!」と叫んで終わる回なのですが。
グレゴリー・フィーリィ『酸素男爵』(ハヤカワ文庫SF)。原著1990年・邦訳1993年(冬川亘)。舞台は月。ははーん、月といえば酸素がない。酸素の供給権を独占する酸素男爵が君臨しているんだな?と思ったら、そうではない。
思いきりネタバレしてしまうと、物語を支えるSF技術のひとつ孤立波隧道(ソリトン・トンネル)によって人類は金星の大気を「かっぱぎ」レーザービームみたいに月に転送し、今や(未来だけど)月は大気を持ち酸素に困らない、外惑星の衛星群の住人から「こっちに酸素よこせよ、ソリトン転送でこっちがかっぱぎたいよ」と思われているテラ化した世界なのだ。
さらにぶっちゃけて言えば酸素男爵は物語にほぼ登場しない。原題ではTHE OXGEN BARONSと複数形な彼ら彼女ら。訳者によればBARONSは「新聞王」「石油王」みたいな使われ方もする語だが「語感のおもしろさをとり」男爵と訳した由。要は月のみならず太陽系の酸素にまつわる権益をあやつり享受する大立者どものことらしい。が、彼ら彼女らが物語の全面に出てくることはない。なかなか純度の高い「がっかり」ではないか。
とはいえ物語自体は「がっかり」とは縁遠い。主人公は爵位とも権益とも(少なくとも当初は)無縁なガルヴァーニッホ。フロンティアにおいて組織や企業に隷属せずフリーランスで生きていこうと思えば、しぜんと零細実業家にして自営業者・発明家も兼ね山師っぽい役回りになるだろう。そんな彼が冒険に巻き込まれ、言うなれば「息もできないほど」ひどい目に遭いまくる。具体的には乗ってた航宙機を仕事仲間もろとも爆破され、爆発で浴びた放射線で内臓をボロボロにされながら月の裏側に不時着し、敵に追われ、味方にこづかれ、泥に呑まれ、氷水をかきわけ、奴隷のような下級労働者たちに紛れて労役しながら逃走のチャンスをうかがい…「他の作品でいうと何に近い?」「うーん、『イワン・デニーソヴィチの一日』かなあ」(よく憶えてないけど)
テラ化したとはいえ過酷な環境。そして作者はその過酷な環境を、特殊スーツの機能からハッチの開閉まで丁寧に描写することで、一行も読み飛ばせない濃密な世界を体験させる。『天空の城ラピュタ』で、着ているシャツを筋肉でもってズタズタに破りポーズを取る親方に後ろからおカミさんが「誰がそのシャツを縫うんだい?」が言い放つ場面があるが、言うなれば「破れたシャツを誰が縫うか」ばかり考えてるような語り口。SFだから何か不思議なペーストを固めたような謎のハイテク食料が自動販売機の出口みたいにテーブルに転がり出てくると思ったか?地衣類でも食いやがれ!
…いや、実際には食事描写はほとんどないのだが、後半に伝聞で登場する「涙目でヒレ肉が切り取られるのをがまんし、また新たに肉を生長させるべくヨタヨタ歩き去っていくステーキ用幼獣」は悪い想像力を刺激する。脂身を適度に含んだ「ハギス」のような肉瘤が育っては本体との付け根がどんどん細くなり、ついには果実みたいに自然に落ちる肉用獣はどうかとか…話が逸れました。

外面からズタズタ、内面(内臓)からもズタズタにされ、低重力のため山脈のようにそそりたつ上げ潮(月の裏側・地球に引っ張られたその頂点で「海」は凍りつく)でシャーベットになりかけた主人公は、艱難辛苦のあげく亡命者としてスペースコロニーに受け容れられるが、そこでかけられる言葉は「あんたはここで仕事口を捜そうと思ったことはないのかね?」うわーつらい。冷たい方程式なみに厳格な世界。SFだったらそのへん、少なくともしばらくは何とかならないの?
この「仕事口を捜さないの?」が「きわめつけ」と思ったら最後の二章=第四部でガルヴァーニッホはさらに酷い目に遭い、第五部でようやく自由らしきものを手に入れる。
この最後の酷い目は今までの物理的な仕打ちとは次元が違う。まあ物理的な仕打ちでもあるのだけど心にズキズキ響く。実はSFでは頻用されるアイディア(次に読んだSFでも出てきた)なのだけど、使われかたが独創的で息を呑んだ。
そしてその分、第五部の開放感が際立つ。ストーリー的に主人公が制約から逃れるだけではない。これまでパッキンひとつ緩ませず、意識的な動作なしには歩く一歩も呼吸ひとつも出来ない感じで(異世界を体感させるために)続いていた描写が、格段に楽になる。これもSF的な作品でよく使われてきたトリックだが、少なくとも非常に効果的。
訳者はあとがきで本作を「惜しいことに(中略)意あまって力足らず(というより後半で息切れして力尽きた感がある)」と評し、第四部・五部での書き込み不足を指摘している。たしかに「そのへんはどうなん?」と不完全燃焼な部分もあるけれど、個人的には第四部のアイディア・第五部の転調のあざやかさこそ捨てがたいとも思うので「訳者あとがき」から先に読んで、先回りで「がっかり」する人のないよう、逆にかばいだてする次第です。思わぬ拾い物でした。やっぱり本は、読むに限る。
* * *
しかし2021年1月現在に意識を戻すと、数十年先の酸素不足どころか、目の前のたかがウイルスひとつにも苦慮する現実の人類は、月をテラ化したりスペースコロニーや外惑星にまで居住地を広げる技術力は「がっかり」するほど不足してるのだなあ、と改めて実感させられる。
いや、それは技術自体が不足してると言うより、技術を開発し普及させる経済力や生産力・あるいは政治力などの圧倒的な不足、なのかもしれない。どんなに可哀想なロボットを操っても(思弁を弄しても)、土(誰かがシャツを縫わなければいけないという現実)を離れては生きられない。「誰がそのシャツを縫うのか」的なディテールに異様なほどこだわった『酸素男爵』を読むことで、得られた知見ではあります。
デーハーな表紙から物理法則など平然と足蹴にするワイドスクリーン・バロック的な作風(※実はちょっと苦手)を想像してたら、真逆のとことん実直SFでした。実は自分は映画だけで原作未読なんだけど、火星でジャガイモ作るSFとか好きなひとに向いてるかも…
| (c)舞村そうじ/RIMLAND |
←2102
2012→
記事一覧(+検索)
ホーム

|